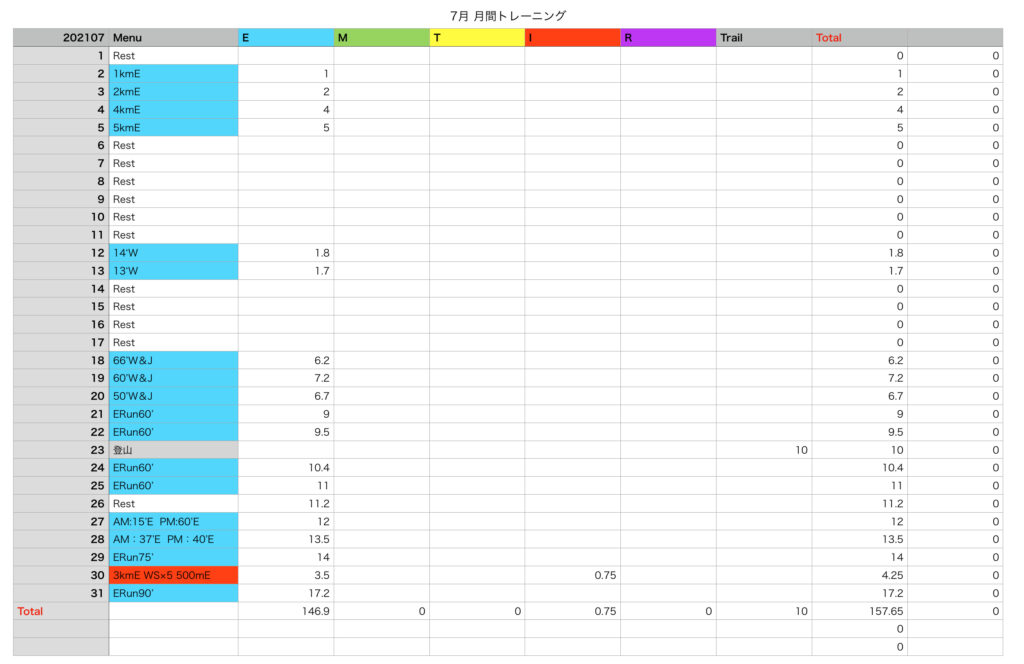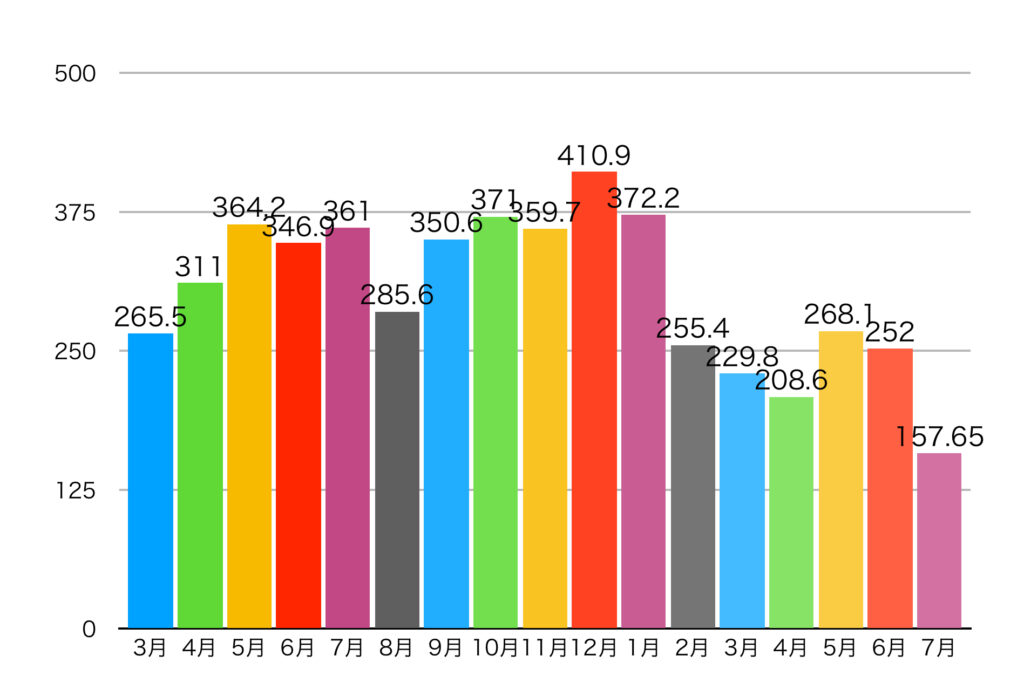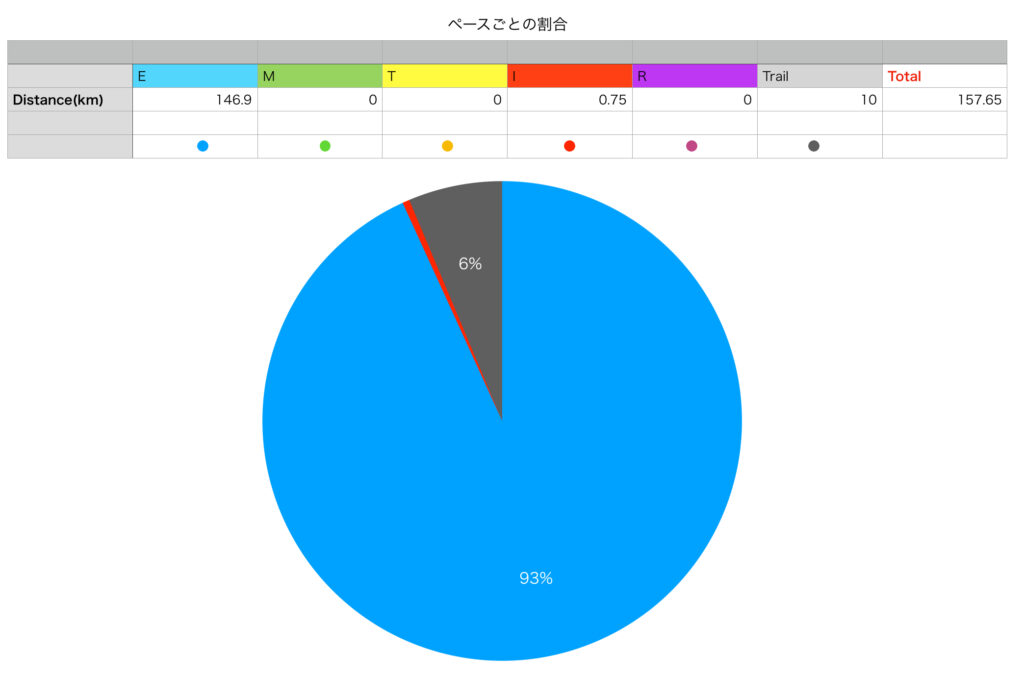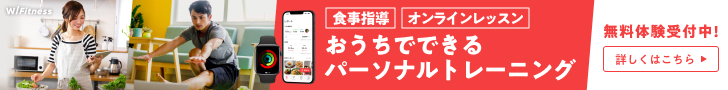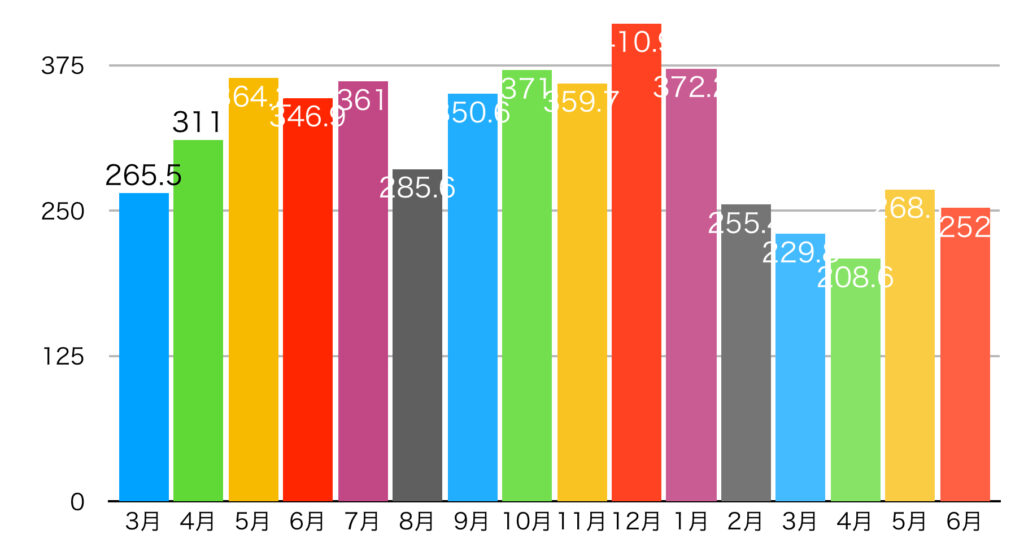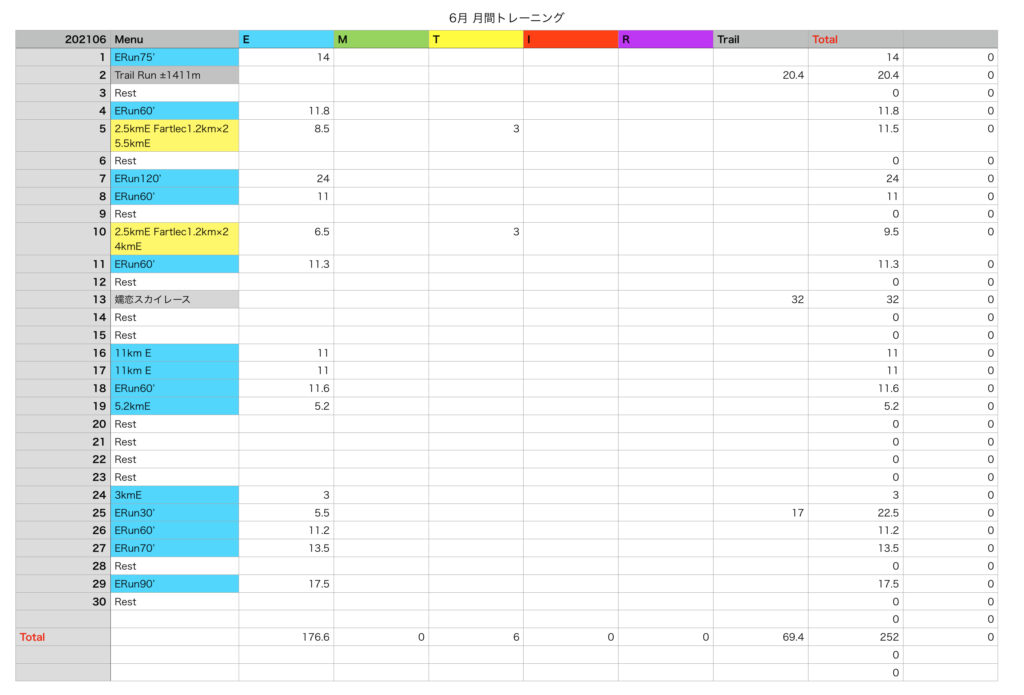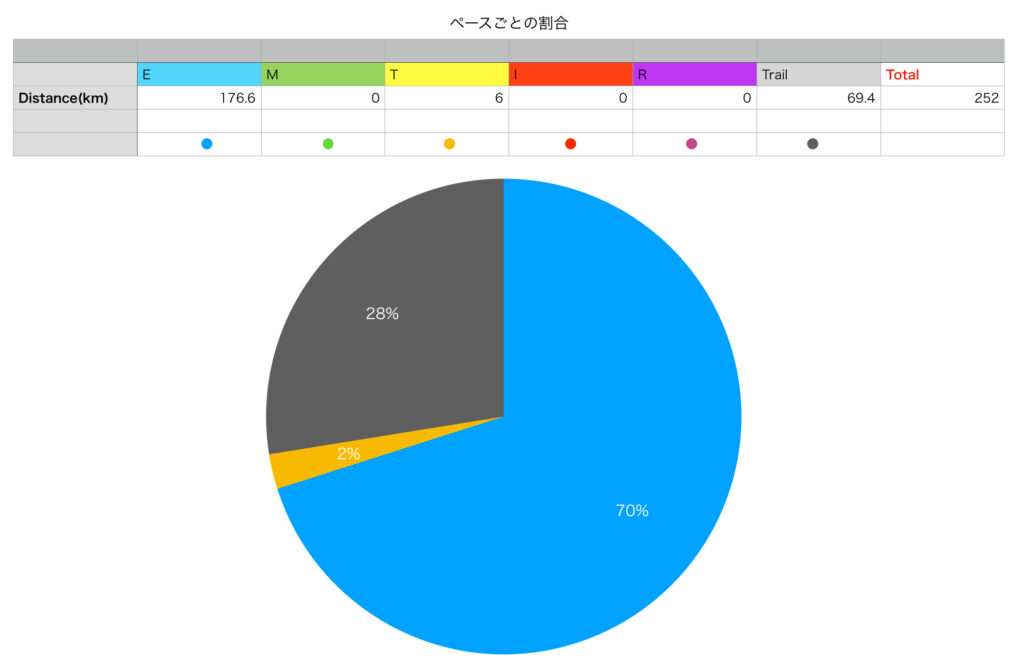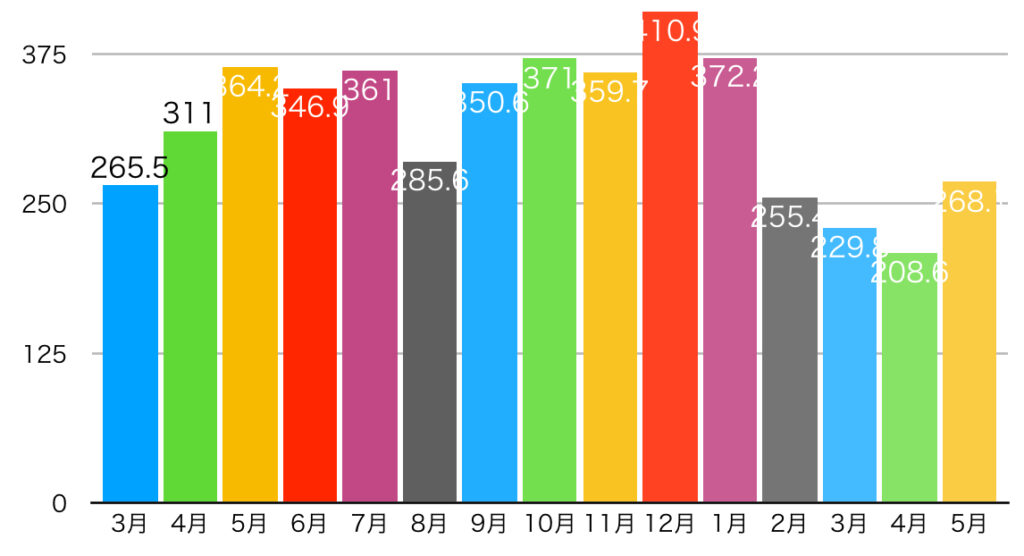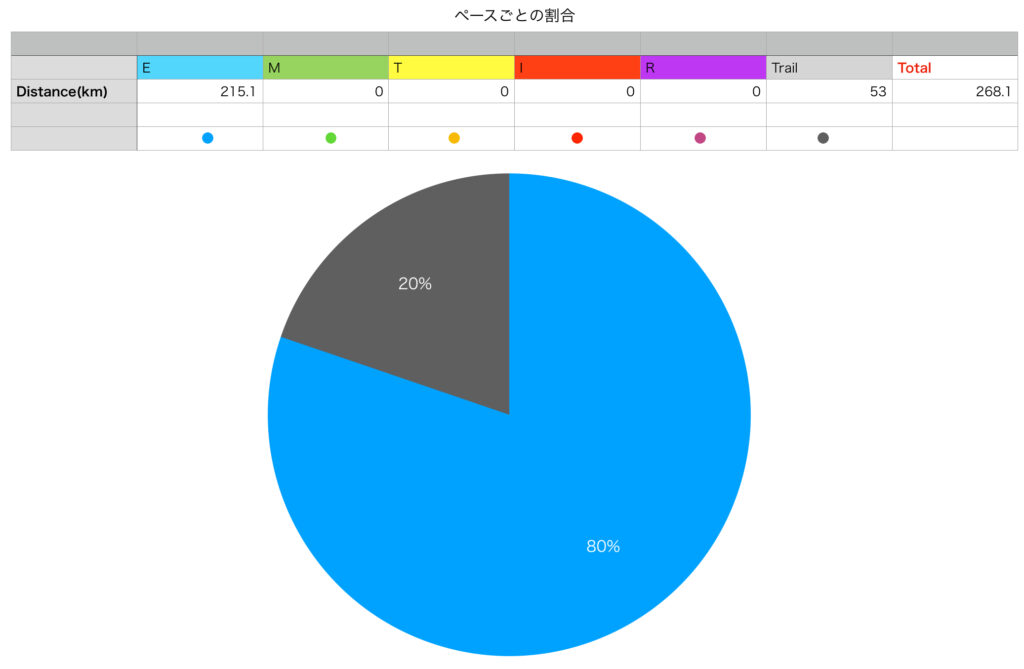こんにちは、ランマニアです。
昨日、トレイル界に衝撃が走った中国の事故。
ネットニュースを見る限りではまだ速報的な記事しか目にすることがなく、これだけをみてああだこうだいうのもどうかと思いますが、いずれにしても恐らくこれだけの死者を出してしまったスポーツ種目は過去類をみないのではないでしょうか(もしかしたら、トライアスロンとかで大規模な海難事故があったかもしれませんが)。
記事に対するコメントや何人かの方のブログを見ますと、本当に見え方、考え方は様々です。
ただ、現時点の情報量だけで、ある特定の観点からある側面だけを「断罪」するのもどうだろう、というのが正直な感想です。
確かに、運営側の杜撰なリスクマネジメントが原因だった可能性も否定できませんし、参加する側の山岳レースに対する意識の問題ももちろんあるのかもしれません。
しかし、今回の事故を、例えば列車の脱線事故や航空機の墜落事故のような「限りなくゼロリスクを目指さなければならないもの」と同じ観点、そしてそれらと同列で論じるのはどうなのだろう、というのが、現時点での私の考えです。
もちろん、今回事故に遭われた方や遺族の方、それから関係者の方々の心情は想像を絶するものがあり、そうした方々と同じ立場に置かれたとしたら、同じような考えはできないかもしれません。
立場が変われば考えも変わる
気分が変われば考えも変わる
これはどんなことにも当てはまることで、だからこそ、ある一つの出来事を一定の価値観や考えだけで断罪してはならないと思うのですね。
(そういえば、最近こんな秀逸なツイートがありました)
そう前置きした上で、いくつか自分の考えをまとめてみることにしました。
そもそも「死」は身近に存在する特別でないもの
本当に事故に遭われた方や遺族の方の心情を無視して言ってしまっていますが、私自身、最近特にこれを感じるようになっています。
20代、30代の初め頃にはまだまだこんなことは考えたこともなかったのですが、40を過ぎた頃でしょうか。やはり生きていると色々なことが起こるのですね。「よくここまで生きて来られたな」と思うようなことに、そこそこ頻繁に遭遇するわけで。
また、周囲でも何もかも順調にことが進んでいる人なんて1人もおらず、変な話「ここまで生きてこられただけでも幸運なこと」に思えてしまうほど、本当に身近な人の人生一つとっても色々あるわけです。もちろん、若くして亡くなった知り合いもいます。
とにかく、生きていればもう死は避けられず、それをいかに防ごうと予防線を張ったとしても、予期せぬことで命を落としたり、危ない目にあったりするのが人生だと思っているのですね。
これは、何も「危ないこと」をやらずに、普通に生活していたってそうだということです。
人間は「生きているから死ぬ」のです。何で死ぬかは誰も予想ができず、それは生きている以上いつ訪れてもおかしくない。そう考えているのです。
行動することは「死のリスクを高める」こと
そうした前提に立った上で毎日の生活を送っていると、もう「行動することは死に向かうこと」と言えなくもない状況だとわかってきます。
例えば、様々な状況下における「死の確率」みたいなものがあるとして、それが家にいる時が1%くらいだとすると、多分、車を運転するなどということはそれが数十倍に跳ね上がると考えられます。
あるいは、リビングで横になってTVを見ているその時の確率が0.5%くらいだったとして、その後我々が大好きなランニングをしに行ったとすれば、それだけで死に遭遇する(心臓発作、交通事故等)確率は30%くらいになるのではないかと、というくらい、死ぬ確率は跳ね上がりますよね。
しかし、じゃあ死ぬリスクが高まるなら何もしないのかと言えば、決してそうではなく「危ないかもしれないけどそれを言い出したら何もできないから、そんなことを考えずに色々と行動する」というのが現実だと思います。
スポーツをするということは、それだけで死と隣り合わせ
そんな身の回りが「危険だらけ」な人生ですが(ていうか、野生の生き物は基本そう)、その中でも相当に「危険な行為」が実はスポーツだったりします。
スポーツは「身体活動」です。
身体を動かすのがスポーツであれば、もうそのものが物理的に「危険」を伴いますし、体の生理的なバランスを著しく崩しながら取り組むことになるのです。
特に、「走る」なんて行為は「いつ死んでもおかしくない行為」とさえ思える運動だと思っています。
なので、もう本当に縁起でもないことを言ってしまうと、ランマニアはかれこれここ10数年、毎日走りにいこうと玄関を出て扉を閉める際には「これが最後になるかもしれない」ということは、常々考えてしまいます。
走り出して数歩で心臓が止まるかもしれないし、その道の角を曲がったら車に轢かれるかもしれない。
そうした「危険」の数々をくぐり抜けて帰って来れれば、今日も幸運だった。そう思うようにしているのですね。
で、何が言いたいか、もうお分かりですよね。
そもそも、そうした日々のジョギング・ランニングだって十分危険な行為なのに、それを2000m級の山々で行うトレイルランニングはもちろんのこと、肉体の限界ギリギリのペースを攻めて42kmも走り続けてしまうフルマラソンだって、もう文字通り「死ぬ覚悟」で取り組むほどのスポーツだということです。
リビングで寝っ転がっていることに比べれば、恐らく死のリスクが100倍くらいに跳ね上がるほどのことをやっていると言っても過言ではありません。
「正常性バイアス」でやれてしまう私たち
では、なぜそんな危険なことを、こうまでして普通にやれてしまうのか。
ここには、私たち人間が陥りやすい「楽観的思考」、「正常性バイアス」というものがあります。
人間は、何か危機的な状況が迫りつつある時でも、何の根拠もなく「自分は大丈夫だろう」「まあ、なんとかなるだろう」という楽観性が優先されてしまう傾向があります。
これから「起こるかもしれない」目に見えない「異常」よりも、今目の前に見えている「正常」な状態の方に思考が支配されやすく、この正常な状態が想像もできない危機的な状況に変貌するなどということが、文字通り「想像できない」のですね。
特に、いつも走りに行くたびに無事に帰って来れれば「今日も大丈夫だろう」と無意識のうちに考えるわけで、それが「死ぬかもしれない」という危険性を、いつの間にか忘れさせてしまっているのです。(いや、だからこそ人間は色々なことにチャレンジできるのですが)
この人間の、誰もが持つ傾向を「さも自分だけはそうでないような物言い」で非難するのは、果たしてどうだろう、ということなのです。
今回の事故の様子を見ていますと、運営側も選手側も同様に、この正常性バイアスが強く働いてしまっていたのではないかと、色々推測しているのですね(予測が非常に難しい気象条件もそれを後押しした可能性が高い)。
山における正常性バイアス=「山を舐める」
こう短絡的に考えるのは、果たしてどうだろう、ということです。
電車に乗ることや飛行機に乗ることとは根本的に違う「参加」
そしてもう一つ、いくつかのコメントから考えたことがあります。
それは、今回の事故を「列車が脱線した、どうしてくれるんだ!」「飛行機が墜落した、安全基準はどうなってるんだ!」と同じような理屈で語られている記事があったということです。
電車や飛行機などの公共交通機関を利用する際は、色々な危険性はあるものの、ある程度「ほぼ100%の安全」を前提としてこちら側も利用しています。
乗る前に「脱線するかもしれませんよ」「堕ちるかもしれませんよ」などと注意されてから乗る電車や飛行機なんかありませんからね。
一方で、トレイルランニングなんていうスポーツは、「死ぬかもしれませんよ」と暗黙に言われているスポーツだと思っています。
そして、そのことを「参加者も理解している」という点が大きな違いだと思っているのです。
電車に乗る際、誰も「死ぬかもしれない」などと思って利用する人はいないと思います。
しかし、トレイルレースは「死ぬ危険性のあるレース」という認識のもと「参加」をするわけです。
それは、運営側が個人の体の状態や天候などに代表される自然の力を、全てコントロールすることは不可能だからです。
ですから、今回の事故の原因全てを運営側の責任にすることは、列車の脱線や航空機の墜落などと同列に捉えているのではないかと勘繰ってしまうのですね。
最も恐れているのが「危ないことはやらなければいい」
今回の事故の責任については、もうそれは法廷が決めることで、我々外野がどうこういうものではないと思っています。
亡くなった方は気の毒だったし、その遺族の方にしてみれば運営側を追及したくなるのは当然のことだと思います。
ですが、我々はそれについてこうだと断罪できかねる理由は今まで書いてきた通りです。
一方ここで、私自身最も危惧しているのが「こんな危険なスポーツはやめた方が良い」という風潮が蔓延ってしまうことです。
もうすでに、別のところでも「トレイルレースは禁止」という意見もありました。
もちろん、人それぞれ様々な考えがあるのはわかるし、それはそれで否定するものではありません。
しかし、もし、この「危ないからやめる」理屈が通ってしまうと、もうほとんどありとあらゆる「スポーツ」自体ができなくなってしまうのですね。
波や海水温の影響を受けるからトライアスロンは危険だ。
時速100kmを超えるスピードが出るアルペンスキーは死ぬ可能性がある。
そのほかにも、スキーのジャンプ、乗馬、ラグビー、アメフト、等々、上述した通り、スポーツはみんな危険で「死と隣り合わせ」なんです。
確かに、今回の事故は一度に多くの死者を出してしまった異例の出来事でした。
当然、運営側の対策で防ぐことができた部分もかなりあると思います。
だからこそ、もう一度その危険性を再確認して対策をし、参加者側も運営側も「正常性」に振られたバイアスを「異常性」にシフトさせる機会にしなければならないと考えています。
そして危険を理由に活動をやめるのではなく、危険性を最小限に止める努力を、参加者のできること、運営側のやるべきことを整理して行い、活動を継続していかなければならないと思っています。